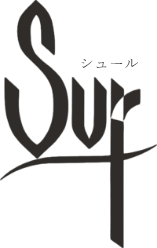深く濃い青が、池に映り込んでいる。その空の青に通じている一本の道を息を荒くしながら一歩、また一歩と歩みを進める。一息入れて、振り返れば、今しがた登ってきた道の向こうには、ここが火山のカルデラだと分かるように、ぐるりと円形となった底に、さっき出発した登山基地の室堂の建屋が見える。隣では我が家の家人や、友人とその奥さんも思い思いにスマホのカメラで雄大で美しい景色を切り取っている。家人は「もうここまで来たんだけど、私、登れるやろか?」友人の奥さんに「大丈夫!ゆっくり登ればいいから」と励まされている。


しかし、目の前に迫ってきた、浄土山のガレ場は、頻繁に山を登ってきたつもりの僕の目にも、圧倒的な急角度とガレ場の長いルートが続く。巨大な岩から子供の頭ほどの岩がゴロゴロと連なり、浮石や落石にも注意が必要なコースには、「のっけからこれかぁ」と思わず、声が漏れるほどだ。


何度かの休みを繰り返し、浄土山に着いたが、石囲いの頂上はパッとしない。しかし、そこから見る景観は迫力とともにやれやれと思わせるものだった。

眼下に一の越の山小屋。その向こうに聳える雄山の鑿で削ったようなレリーフは圧巻の一言だった。その頂に伸びる尾根道は、ほぼ直登に見える。内心「これは手ごわそうだな、何度か休憩はいれるだろうけど、家人は登れるだろうか?」と本気で心配したほどだ。一の越に進む道を少し歩くと、丸太のベンチがあったので、ここで朝昼兼用の食事にする。目の前には龍王岳の荒っぽい山頂に数人の登山者が見える。そこには登らないが、その頂への憧れに登行意欲は掻き立てられる。
買ってきた寿司弁当のお稲荷さんが、ほんのり甘くて、染み渡るようだ。思い思いに簡単な食事をとり、いざ3000mオーバーへ向けて、コル(鞍部)の一の越への下りを歩みだす。
途中に石積みのケルンのようなものがある。その石済みには、ゴムのようなロープのようなものがグルグルと巻かれている。その後の登山路にも似たようなものがあったが、「んっ、何だこれ?」しばらく歩きながら考えてみる。確かではないが、ヘリコプターでの救助に使うのでは?などと思ってみる。そうこうしているうちに、一の越に着いた。室堂からの石畳を真っすぐ来れば、ここ、一の越に着くわけだが、我々は、苦しくとも素晴らしい景色のために浄土から降りてきたが、ここは激込みだ!日本語以外の言葉の方が多いのではと思うほど外国人も多い。ここの山小屋にも冷たいものなどあるのだろう、にぎわっている。そして、コルではあるが、ここからは槍ヶ岳や笠ヶ岳であろうか?尖った先鋒が望める。

ここからいよいよ、アイコニックな雄山への道を歩くことに、心は踊るばかりだが、いかんせん、筋肉と呼吸がついては来ない。沢山の人たちが雄山までは登ろうと詰め掛けているので、ごった返しているのだが、ここが行き届いているのは上りと、下りの登山路が分けられていることだ!スプレーで上りが黄色、下りが赤と色分けもされているのには、さすがに整備が行き届いているものだと感心する。観光客の外国人の女の子はへそ出しTシャツにデニムのパンツ、靴はニューバランスのいでたちで登っている。英語の喋れる友人は彼女と何やら話している。3000mの山に登りつつも、英語が喋れるっていいなぁと、うらやましく思う。この日は2500mを越えてもあまり酸素の薄さを感じない。6月の唐松岳の高所順応が効いているのであろうか?
目の高さに、先ほど登った浄土山の頂が同じ高さになる。あとは高さにして50m程、距離は100m程だろうか?友人の「もうすぐ、もうすぐ」、「ゆっくり息して」、の掛け声に家人も踏ん張っているようだ。

初の3000mオーバーを完登!はるか遠くの槍ヶ岳と笠ヶ岳をバックにパシャリ!喜びもつかの間、雄山神社にお参りするのだが、立山三山のハイライトは3000m級を渡り歩く立山禅道。生きながらにして地獄と極楽の世界があるとされ、このコースを走破することで一人前の大人として認められるそうで、浄土山で過去を振り返り、雄山で現世を見つめ、別山で未来永劫の世界を体得するそうなのだが、「ああっ、確かに浄土山は地獄の登りだったが、登ってしまえば過去のこと・・・いい思い出。この雄山の頂は、確かに今日、今この瞬間に喜びに溢れ、幸せを感じている・・・そしてまだその踏みあとを残してはいないが、別山で未来永劫を体得しよう」などと、1人勝手にほくそ笑むのおではあるが。さて、小屋のような社務所で¥700を払い、そのさらに狭い雄山神社に25名ほどが押し合いへし合い、ぎゅうぎゅう詰めで祝詞をあげてもらう。まず、神主さんが、静かに膝をついて頭を垂れてください・・とお告げになる。そして風の音以外に何いも聞こえない3003mの境内に太鼓の音がポンポンと響く、柏子見、柏子見・・と祝詞があげられるが、ビリビリと体がしびれるような感覚に包まれ、もう何もないような感覚に陥る、宇宙に放り出されたような妙な、不思議な感覚に包まれ、もう何も聞こえない。しばらくの後、「はあーっ」という皆さんの声に我に返った。「何だったのだろう・・」
神主さんが、おもむろに、万歳三唱しますか?の声に皆さん、はい、やりましょう。そして、掛け声とともにバンザーイ、バンザーイ、バンザーイ・・パチパチパチ。賽銭を入れて二礼、二拍手の参拝を行い、神社を後にする。

さあ、次は大汝山。禅道最高峰3015mの高みへと進む。ここから先は山小屋泊の登山者だけになるので、賑わいは遠ざかる。相変わらずのガレ場だが、アップ、ダウンが多くなる。


この山は雄山以上に、岩だらけの先鋒だ。近づいてくるほどにゴツゴツとした岩肌に寂寥感が広がる。この山も登頂する予定だったが、時間に追われていた。山小屋からは、15時までに入ってほしいと言われていたからだ。やむなく、断念して先を急ぐ
それでも、もう15時には間に合わない。内蔵助山荘に電話を入れ、「富士ノ折立の稜線上にいるが、入室時間には間に合わない、もう少し時間をください」と告げ、更に急ぐ。

折立には、何とか登頂したが、皆、疲労が滲んでいる。記念撮影もそそくさと済ませ、真砂岳へ続く鞍部の稜線を足を引きずるように進む。その道を進みながら、「ああっ、時間の計画が甘かった」と後悔する。ここまで5時間半が経過していた。いつも、単独で登る自分のペースに少しのプラスαで大丈夫と考えていた。まさに後悔先に立たずだった。

真砂岳の頂上へ着いたときは、15時半を過ぎていた。が、後ろを振り返ると女性陣は、途中に腰かけて休憩中だ。僕は、早く早くとは言えなかった。曖昧だった自分の認識の甘さをさしおいて、言えるわけもなかった。ゆっくりと追い付いてきた2人に、さあ、あとは5分ほど下るだけ。頑張ろう!と伝えるしかなかった。
続きは、また次回に。