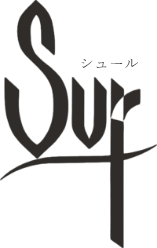午前6時半過ぎに到着した駐車場はすでに満車で、1台も車は止められない。ビッシリと詰め込まれた登山道わきの駐車場を後にして第2駐車場へ車を回すが、ここも一杯だ。止む無く第3駐車場へまわる。
去年もこの山域の別ルートをお盆に登ったが、そのルートはこの山のメインルートを登って頂上を目指すものではなく、1400m程の名もなき頂から、美しくも無慈悲な壁を眺めるという登山だったが、ガスに巻かれて頂上は見えず、今となっては登れない(縦走禁止)壁を、昼食も取らず只々飽かずに眺めて降りてきた。結局その登山口駐車場には、朝、止めた私の車だけが駐車されていた。
さて今年は、更にその前年、2年前に登ったルートで上を目指す。ここもまたメインルートではないので登山者は少ない。観光客と登山者でごった返している駐車場から大山寺の山道へと石畳を進む。まだ7時過ぎなので山道脇のカフェやお土産物屋は空いていない。ご夫婦の登山者が、「こんなに人が多いんだから、早く店を開けてくれればいいのに」などと勝手なことを言っている。やはり、人込みではいろんな喧騒が聞こえてきて、好きになれない。
大山寺から大神山神社の石畳を過ぎて、ようやく地道に入ると、もう人はいない。行者登山口に到着して、いよいよ登山をスタートさせる。森の空気は濃密で、酸素濃度が高いと身体が教えてくれる。気温も22~23℃くらいだろうか?立派なブナの木々の間から木漏れ日が差し、すこぶる快適な登行を後押ししてくれているかのようだ。
スキー場方面からのコースとの合流地点で尾根道に出る。ここで一息入れる。もう少し進めば、大山の北壁が樹間に見え始めるのが、このルートの楽しみだ。

下宝珠、中宝珠、上宝珠を過ぎた辺りからアップダウンを繰り返し、右に北壁、左に三鈷峰がそびえる。

ガスを被っていた山頂の連なりも晴れ渡り。標高は1700m程の山ではあるが、アルプスを思わせる山体が目には眩い。傾斜の増した斜面に設置してある固定ロープを使って登るが、いつも、「これ大丈夫?いつ設置したロープ?」不安になる。しかし、ツルツルの斜面に摑まって登るにはきつい。やはり使わせていただくことにする。
三鈷峰の山頂直下のT字路に到達した。左に進めば、その山の頂だが、今回の登山計画は天狗ヶ峰や槍ヶ峰に通じる縦走路にある、1636mの名もなきピークへの登行だ。右へ進み、お花畑で有名なユートピア小屋の方面へ進むことにする。残念だが今年の猛暑と少雨のせいだろう、本来なら花のピークを迎えて盛りだろうに、わずかな花しか咲いていない。大山フウロだろうか、それがつつましく咲いているだけで、青葉が生い茂って風に揺れている。

ユートピア小屋を過ぎ、さらにダイセンキャラボクの藪をかき分け、最初のピークへ。振り返れば今しがた登ってきた登山路と、その向こうに、三鈷峰が見えている。

ガスも消えて、すっかり晴れ渡った北壁のピークが目の高さに連なっている。

2番目の丘を越え、目指す1630mの頂は人が4人ほど座ることのできる広さのある丘だが、目の前には天狗が峰が圧力をもって立ちはだかっている。

その向こうには槍が峰も見えている。

槍と天狗の間を登山者が縦走している。4人のパーティー、3人のパーティー、2人のパーティー、見えるパーティーに単独の登山者はいないようだ。今いる場所から天狗に向かって道が続いているその道をなぞるように子細に眺めてみる。今の自分の力なら天狗の頂上に立てるだろう。足元の幅40cmのざれ場も、その先の草付きの急な登りも、直下の岩場も突破できる。間違いなく天狗の頂に立てるだろう。
心が、あの山頂に立ちたいと、ざわついている。何度も眺めまわした。いける、行こうか。しかし、家族の誰にも天狗に登るとは伝えていない。もちろんここはスマホも通じる。でも伝えれば止められるだろう。モヤモヤしていた。
諦めた。登ることはできるだろうが、あそこから一人で帰ってこれるだろうか?この太古の昔に成り立った古い火山は風化とともに、ガラガラと崩れている。山体の沢沿いには真っ白な岩くずが大河のように流れ下っている。
もろい岩肌を一人で下るのは勇気以上のものがいる。こういう時はパーティーの登山者がうらやましく思える。ただチャンスがあれば、そのとりつきまで行って、登山路の状態や岩の質を確かめてみたいと思っている。やはり行ってみないと分からないこともあるので、次回の宿題だ。下山を開始した。思いはあるが、今日もいい山だったと満足している。
大山寺まで降りてきたが、この山道の石畳はいつも濡れていて滑る。初めて下った時は何度も転びかけ、身を固くしたものだ。けれど、もう何度も上り下りを繰り返したこの山道の歩き方にもすっかり慣れて、参拝する観光客の足通りとは比べ物にならない速さで降りられるようになった。要は岩角の上に、もしくは平らな石に足を置くことだ。それと、真ん中を歩くことに尽きる。
今朝、登りがけには開いていなかった山道脇の店も観光客でにぎわっている。ラーメン屋の前には多くの外国人が、20人ほど並んでいる・・・思わず、そんなに!と声が漏れた。静かな山を下りてにぎわう観光地に降りてくれば、今日の山の満足感と下界の煩わしさが同居したヘンテコな気分になる。