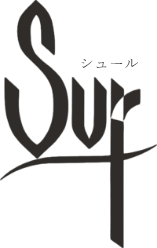窓を開けると、すでにピンクに染まった白馬三山が目に映る。
映画や小説のような壮絶な赤でもなく、灼熱した赤でもない、柔らかな朝日を浴びたピンクのモルゲンロートの美しさとともに、ほどける様な優しい気持ちになる。
朝の4時半だ。

いよいよ、2696mの高みを目指して、登山を開始する。スッキリと晴れ渡っているが、昨日同様、気温は高めのようで、長そでの上に半そでを重ねただけの軽装でスタートする。
山肌は徐々にピンクからオレンジ色に変化し、昨日、雪もつかない険しい表情を見せていた鹿島槍や五竜岳も曙光を受けて穏やかに見える。


振り返れば、戸隠山、高妻山、妙高、雨飾山までも見える。
ゴロゴロした岩の蛇紋岩帯が昨日の偵察行の第3ケルンの先まで続いているが、そこまでは危険のない整備の行き届いた道。
早朝の誰もいない景色を楽しみながら快調に歩みを進める。その、景色だけではなく、足元の草花も鳥のさえずりも、すべてがほほ笑んでいるかのような気持ちに包まれる。
八方池を過ぎ、昨日の最終地点を過ぎれば、ここからは未体験の登行になる。
ワクワク感と緊張感の入り混じったモヤモヤした気分がなんだか変な感じだ。
八方尾根をしばらく進むと最初の雪渓が現れた。やはりアイゼンを携行してきてよかった。
気温の高さからか、2300mを越えたこの雪渓はグズグズの雪で、一歩進めば半分はずり落ちるという有様だ。
しかし、その雪渓には新しい足跡はなく、前日に頂上を往復した登山者はいないようで、微妙に不安感を覚える。
登山アプリを確認するが、間違ってはいない。土日の登山者の踏みあとは夏の日差しと高い気温で溶けたのか、殆ど判らないような曖昧なものになっている。
やっとの思いで雪渓を越えて地道にたどり着くが、履いたアイゼンを脱ぐのがもどかしい。
尾根に続く丘を越えるとまた雪渓だ。あとで分かることだが、ここで道間違いをする!またアイゼンを装着し、雪の原っぱに進む。
やはり上の雪渓もクラスト(雪の表面が凍って硬くなった部分)のくの字もない。
個人的にはクラスとした雪にアイゼンの爪が食い込むときの感触が好きだが、6月中旬にそれを望むのには無理があるか。
こちらの雪渓は広く、越えるのに息切れするほどだった。途中振り返ると、林の中央に登山道らしき道が見える。
思わず”そっちかよ”と声が出る。どうやら夏道と冬道があるようで、アプリは冬道を指していたようだ。苦しい雪渓だったので、”クソッ!”と毒づいた。


そういえば、雪渓の手前にダケカンバの林があった。
森林限界を超えてからは石と岩ばかりの道、植生の逆転現象がみられるのも、この山のいいところだ。

そのダケカンバの林あたりから現れたのは、みな、ふっくらとしたライチョウたち!



もうすっかり夏の衣装に衣替えしたライチョウたちは人を怖がるでもなく、それなりの距離を保てば写真撮影オッケーよ!
とばかりにそこここでポーズを決めてくれる。カワユス・・・



2500mが近づいたころから、息が苦しくなってきたように思う。
別段、酸素がそれほど薄くなったわけではないだろうが、数十メートル登っては立ち止まり、また登っては立ち止まりと、休むことを繰り返しながら体を押し上げる。
目の前には”不帰の剣”がそれぞれにそそり立ち、いよいよそれは強烈に個性を放ってⅠ峰、Ⅱ峰、Ⅲ峰が天狗の大下りを伴って迫ってくる。
そして、目的の唐松岳も尖った穂先を空に向かって”すっく”と立ち上げている。


だが、足元は切れ落ちた痩せ尾根、景色ばかりに気を取られてはいられない。
大きな岩を木の根を掴んで回り込まなければならないところでは、7,8m落ちれば、雪と土の溝が口を開けている。
誰もいない単独行では、たとえ初心者コースと言われる道も、確認しなければ、ご迷惑をかけるだけだ。
このコースでは丸山ケルンより上がそれにあたるのではないだろうか。

もうここは頂上直下、振り返れば、その峰の連なりは足元からウネウネとラインを引いて、遥かな稜線が雲の向こうまで続いている。


下から見上げていた不帰の峰々も今は、目線の高さにある。目の前に立ちはだかる名もなき岩山を登り、下り、登り返せばそこが目的の頂だ。

が、鉄梯子とブロックの急な階段に最後の力を振り絞らなければ容易ではない。その尖った尖塔のような岩山は、すでに青息吐息の僕をこれでもかと苦しめる。よろよろと岩山の上に立った。

その名もなき頂からは、山岳写真でよく見る、頂上へのプロムナードが見える。もうすでに300㎖の水は空だ。ザックを降ろすのも面倒だが、仕方が無い。ごそごそとボトルを探して、水をあおると体に染み渡っていく。眼下に見える赤い建物はその週末にオープンする、唐松岳頂上山荘。3日後からの営業で、急ピッチで準備が進んでいるようで、昨日は何機ものヘリコプターが物資を運んでいた。塗り替えられたであろう建物は新築のような趣で、突如現れた人工物はまだ景色になじんでいないようだ。山小屋の前にはなんだかわからないような物資がまだ積みあがっているようで、さぞや天手古舞しているのではと思われる。

頂上への一本道を歩み始める。下りから、最後の登りへ差し掛かると、脇に大きな岩がある。外国人に見せたら叱られそうな、中指を突き立てたようなその奇岩は僕に(〇ァック ユー)とでも言っているようだが、ここまで来たらもう引き返せない。「舐めんじゃねえぞこの野郎、最後まで登り切ってやらぁ!」と気合を入れなおし奇岩を後にする。



頂上は360度に展開する大パノラマ。立山連峰の峰々、登りがけに見えていた五竜岳は表情を変えて後ろ側を見る。それは唐松岳頂上小屋から五竜の頂上へと天空を駆け上る美しいラインが引かれている。不帰の釼や白馬にはもうガスがかかりその姿はチラホラと見えるばかりになった。孤軍奮闘の末に見る美しき峰々に酔いしれていた。風も穏やかで日差しも柔らかい。肌を撫ぜるそよ風の音しか聞こえない、たった一人の誰もいない山頂に心酔していた。などと思っていたが腹が減った。ペコペコだ!行動食のみでここまで来たが、食べねばなるまい。早速山小屋で用意していただいた弁当を取り出し吟味する。おにぎり2個(その1つは赤飯に甘いお揚げさんが巻いてある、もう一つはわかめのふりかけのおにぎりだ)おかずは(海老天、つくねのたれ焼き、卵焼き、焼き魚、柴漬け、きんぴらごぼう)これがまた、すこぶる美味い!揚巻き赤飯は、お揚げさんの甘さが疲れた体に染み渡りその他のおかずも、小ぶりながら飽きの来ない味付け。あっという間に平らげた。

食後も一人、山々を眺め黄昏ていたが、その時左目の端にそれをとらえた。遥かに遠いガスのかかったその向こうにひと際尖った黒い影を・・・”槍だ”槍が岳だ。正直、感動した。
それが見えることなど微塵の期待もしていなかった。今いる山頂から槍ヶ岳までの間には爺ケ岳、蓮華岳、針ノ木岳、烏帽子岳、野口五郎岳などの北アルプスのジャイアントが数10キロにわたってが居並ぶ。それはガスの切れ間に時々現れては消えるを繰り返し、やがてガスに巻かれて見えなくなった。しかし、確かに居た・・・消えてしまったのを潮に下山を開始した。
気分は高揚していたが、”遠足は帰るまでが遠足”。登山は”車に到着するまでが登山”。登山の事故は圧倒的に下山時に起こる。慎重にと言い聞かせて下山する。下の雪渓まで降りてくると、今日初めての登山者に出会う。挨拶を交わし、情報を交換する。「上はどうですか?」の問いに「この丘の向こうにもう一つ大きな雪渓があります。雪の状態は・・・」とお伝えして「気を付けて」の声をかけ分かれる。山小屋泊以外の登山者は始発の6:40分のゴンドラで登ってきたものと思われる。この日は多くの登山者とすれ違うのだが、中にはTシャツ1枚にデニムのワイドパンツにスニーカー、肩にトートバッグと云ういで立ちに???「どこまで行くの?」彼「上まで」・・・「いやいや、その靴じゃ無理だよ、大きな雪渓もあるし、渡れないよ」彼「・・・いや行けるとこまで行ってみます」その後も何人かの方から「行けるとこまで行ってみます」という答えがあった。しかし、そんなことが言えるのは、完全装備と経験豊富な方だけではないだろうか?僕も人の事ををとやかく言える立場にないが、救助や遭難でご迷惑をおかけすることは本意ではない。気を付けたいものだ。
八方池付近まで戻ると、登山者と観光客でごった返している。あいさつ程度にして山小屋に急ぐ。預けていた荷物を回収して、下りのリフトに飛び乗った。登りのリフトには思い思いの格好をした人たちが大勢乗っている。遠ざかっていく山々を振り返り、終わりに近づく山旅に思いが残るが、それは帰りの車で一人噛みしめよう。それより今は蕎麦だ!安曇野で2番目に美味い蕎麦屋に直行した。定休日だった・・・帰りの道路わきに見つけた、安曇野でたぶん12番目くらいのソバ屋で食った。12番目の味も悪くなかった。